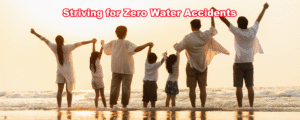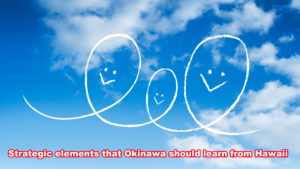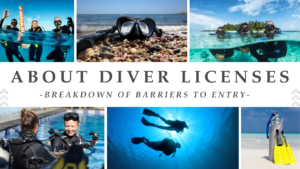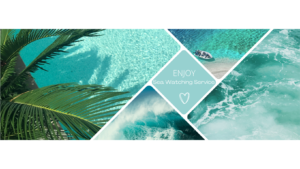水難事故ゼロを目指して
届出制から許認可制への提案 深刻化する水難事故と背景 沖縄の美しい海で近年、水難事故が深刻化しています。2024年の県内水難事故は128件と過去最多を更新し、45人もの尊い命が失われました。観光客の事故も増加傾向にあり、特に外国人観光客の事故件数は前年比2件から19件へと急増しています。一方でマリンレジャー産業は県内で年間推計134億円規模、延べ約161万人が利用する重要な観光ビジネスです。しかし、その 安全対策が追いついていない現状 が浮き彫りになっています。実際、県警が認定する安全優良事業者(いわゆる「マル優」事業者)は全体のわずか3%(109件)にとどまり、多くの業者が安全基準を満たせていないのが現状です。現在、沖縄県では「水難事故防止条例」に基づき海水浴場やダイビング業など5業態に事前届出を義務づけていますが、こうした 届出制だけでは事故防止に限界 があるのではないか…本記事ではその課題を検証し、命を守るために許認可制への移行を提案します。 実例1:マリンレジャーの安全上の問題事例 沖縄の海では特定地域に事故が集中する傾向が見られます。第11管区海上保安本部の調査によれば、例えば本島中部の人気スポット砂辺海岸では過去10年で33人、真栄田岬(青の洞窟)でも32人の人身事故が発生し、離島でも伊計島や石垣島米原ビーチで各25人、新城海岸(宮古島)で19人と多発しています。こうした事故の約7割は監視員のいない自然海岸で起きており、しかも事故当事者の約9割がライフジャケット未着用という現実があります。 安全意識の欠如や指導不足が重なり、「わずかな気の緩み」で命を落とす事故が相次いでいる状況です。 第11管区海上保安本部が作成した「マリンレジャー中の事故多発マップ」。沖縄本島周辺の主な事故多発地点が示されており、死亡事故の約9割でライフジャケット未着用だったことが強調されている。各地で事故が集中し、地域ごとに安全対策の強化が求められている。 さらに、悪質な無資格営業の問題も指摘されています。沖縄県内のマリンレジャー事業者への聞き取り調査では、「無届け業者や反社会的勢力とつながる業者が存在し、消費者トラブルが増えている」「悪質業者への罰則や取締りが弱く、野放しになっている」という声が上がりました。 例えば2024年夏、本部町の海岸では水難死亡事故が立て続けに発生し、管
沖縄の観光ブランドはサンゴ礁とともに
守るべき海の宝と私たちにできること サンゴ礁破壊の現状とその深刻さ 沖縄の海を彩ってきたサンゴ礁が、今、危機に瀕しています。近年、サンゴの大規模な白化現象(サンゴが真っ白に変色する現象)が頻発しており、例えば2022年9月時点では八重山諸島の石西礁湖でサンゴの90%が白化していることが報告されました。また、日本最大のサンゴ礁域である石西礁湖では、2017年までの間に約70%のサンゴが死滅したとの環境省の調査もあります。サンゴ礁の衰退は沖縄にとどまらず、世界的な問題となっています。IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)は、地球温暖化による平均気温の上昇が1.5℃に達した場合、2030〜2050年までに地球上のサンゴ礁の70〜90%が死滅する可能性があると警鐘を鳴らしています。このまま何も対策を講じなければ、「南の島の美しいサンゴ」は幻となってしまうかもしれません。 サンゴ礁が減少する原因は複雑に絡み合っていますが、主な要因は次の通りです これらの要因が重なり、沖縄のサンゴ礁は年々確実に減少しています。かつて色とりどりのサンゴが群生していた場所が、今では白化し、死んだサンゴや藻類に覆われた岩場になってしまっている例も少なくありません。サンゴ礁は単なる美しい景観ではなく、海の生き物全体の4分の1が暮らす「海のゆりかご」ともいわれており、その崩壊は海の生態系全体に深刻な影響を及ぼします。このまま放置すれば、沖縄の海は取り返しのつかない損失を被る可能性があります。 海外の先進的なサンゴ礁保全の取り組み 世界ではサンゴ礁を守るための先進的な取り組みが行われており、いくつかの地域では成果を上げています。沖縄と同じく、美しい海を観光資源にしている国や地域の成功事例を紹介します。 オーストラリア(グレートバリアリーフ海洋公園) 目的・法制度 運用と成果 パラオ共和国 目的・法制度 行政機関の対応 運用と成果 ハワイ州(米国) 目的・法制度 行政機関の対応 運用と成果 その他の先進事例 沖縄におけるブイ設置の現状と課題 既存のブイ設置状況と管理体制 部分的な導入 全県的には不足 情報不足の原因と他地域での類似事例 科学的データの不足 他自治体の取り組み 地先権者(漁協等)との摩擦要因と解決策 漁業権との調整の必要性 解決策・協働モデル 環境保全効果による経済メリット サンゴ礁
沖縄観光ブランド
アイデンティティ確立の戦略提言 ハワイのブランディング戦略の成功要因 ハワイは早くから官民が連携して「楽園ハワイ」という統一イメージを打ち出し、自然の美しさや温暖な気候、そして「アロハスピリット」を前面にプロモーションしたことで観光客数を飛躍的に増加させました 。そのブランド戦略の鍵は、単なる風景だけでなく文化や歴史に根ざした非日常の体験を提供し、訪問者の心身を癒やす「体験価値」を徹底重視した点です 。 また、2000年代以降はSNSやオンラインを活用し、「自分だけのハワイ」を感じさせる情報発信(カスタマイズ可能なデジタルマーケティング)に注力しました 。さらに、ハワイ州観光局(HTA)など専門のマーケティング組織がグローバル市場ごとにキャンペーンを展開し、どの国からの観光客にも一貫したブランドメッセージ(アロハ精神、マラマハワイなど)を適切に伝えています 。 ハワイはまた、現地住民の生活や文化を尊重し、観光の恩恵を地域に還元することで住民の満足度も高めています 。こうした「温かいおもてなし」と「持続可能で本物志向の観光」により観光客の心を掴み、高いリピーター率(観光客の約7割がリピーター)を誇る強力なブランドを確立しました 。その結果、ハワイという名前自体が世界的に認知された観光ブランドとなり、多くの高所得層を含む観光客が安心して「何度でも訪れたい」と感じる目的地となっています 。 ハワイ・ワイキキビーチの航空写真。統一された「楽園」ブランドと豊富なリゾート施設により、世界中から観光客を引きつけている(ハワイのブランド力を象徴する光景) 沖縄の観光資源を活かした独自のブランド戦略 沖縄はマリンレジャー(透明度の高い海・世界有数のサンゴ礁・ダイビングなど)、手つかずの豊かな自然(亜熱帯の森や希少生物、離島の美しい風景)、そして独自の伝統文化(琉球王国の歴史、祭りや芸能、工芸、沖縄料理、長寿文化)といった多彩な観光資源を持っています。これらは「その土地にしかないブランド」として観光客を惹きつける強みとなります 。 実際、沖縄県も近年「おきなわブランド戦略」を策定し、国内外の消費者に沖縄の本質的な価値を訴求することに力を入れ始めました 。その中核コンセプトは、ターゲットのコア層を「付加価値の高い旅行を好む本格志向の旅行者」と定め、彼らに「日常のしがらみや時間からの解放
沖縄のマリンレジャー業界の課題
沖縄のマリンレジャー業界は、日本国内外から多くの観光客を迎える一方で、 安全対策の不備、環境破壊、規制の甘さ、人材不足、反社・半グレの参入 といった深刻な課題を抱えています。これらの問題を整理し、根本的な解決策を提示します。 1. 法制度と規制の不備 (1) 許認可制の欠如(届出制の問題) (2) 行政の監視体制の甘さ (3) 罰則の弱さ 2. 安全対策の不備 (1) 無資格・無保険の事業者の増加 (2) 水難事故の増加 (3) 緊急対応・救命設備の未整備 3. 環境破壊と観光資源の管理不足 (1) サンゴ礁の破壊 (2) オーバーツーリズム (3) 海洋汚染 4. 人材不足と労働環境の悪化 (1) 業界のブラック化 (2) 外国人インストラクターの増加と問題 5. 反社・半グレの参入 (1) 違法営業の温床 (2) トラブル発生時のリスク 6. 外国資本の無秩序な参入 (1) 環境ルールを無視した事業者 (2) 価格破壊と安全対策の軽視 7. 解決策の提案 沖縄のマリンレジャー業界が持続可能な形で成長するためには、業界の健全化、安全対策の強化、環境保全の徹底、適正な市場競争の確立が必要不可欠です。
マル優制度
沖縄公安委員会のマル優制度について 沖縄県は、その美しい海と豊かな自然環境から、多くの観光客がマリンレジャーを楽しむ地として知られています。しかし、近年の水難事故の増加は深刻な問題となっており、2024年には発生件数128件、罹災者数145人、死者数45人、行方不明者数2人と報告されています。 このような状況を受け、マリンレジャーの安全性向上が急務となっています。 マル優制度の背景と必要性 沖縄県内には3,800社以上のマリンレジャー事業者が存在し、その参入障壁の低さから事業者数が増加しています。しかし、安全対策への取り組みは事業者ごとに差があり、提供されるサービスの質にもばらつきが見られます。 このような状況下で、利用者が安全にサービスを選択できる指標として、沖縄県公安委員会は「安全対策優良海域レジャー提供業者」、通称「マル優事業者」制度を導入しました。 マル優制度の目的と効果 マル優制度は、海水浴場、潜水業、プレジャーボート提供業、スノーケリング業、マリーナ業などの事業者を対象に、安全対策基準を満たす事業者を認定するものです。認定を受けた事業者は、公安委員会から交付された標章(マル優マーク)を掲示でき、利用者はこのマークを目印に安全性の高いサービスを選択できます。 これにより、利用者の安心感が高まり、事業者間の安全対策への意識向上も期待されます。 マル優制度の課題と展望 2024年6月時点で、マル優事業者の指定件数は109件と、全体の約3%にとどまっています。このことから、制度の周知・普及が課題となっています。 今後は、制度の認知度向上とともに、事業者の安全対策基準の遵守を促進し、沖縄のマリンレジャー全体の安全性と質の向上を目指すことが重要です。 沖縄県公安委員会が実施する「マル優制度」は、海域レジャー提供業者の安全対策基準を評価・認定する制度です。この制度により、安全性が確保された事業者を利用者が容易に識別でき、安心してサービスを利用できます。 主なポイント: 利用者は、マル優マークを目印に、安全対策が十分に施された事業者を選択することが推奨されています。  マル優制度の申請手順: 注意点: これらの手順に従って、適切に申請を行ってください。
潜水士免許について
以下に、潜水士免許制度および2018年の特例措置、さらに沖縄における外国資本参入やサンゴ礁破壊の懸念点を整理した資料を作成しました。 潜水士免許の概要 目的 取得条件 レジャーダイビングとの乖離 ダイビングインストラクターと潜水士免許の関係 ダイビングインストラクターの業務範囲 潜水士免許が必要とされる理由(日本人インストラクター) 2018年の特例措置(高気圧作業安全衛生規則の改正) 特例措置の概要 不公平感の指摘 参入障壁の低減と影響 参考資料 : 厚生労働省「高気圧作業安全衛生規則改正に関する告示(2018年)」など 沖縄での問題点とサンゴ礁破壊への懸念 沖縄の現状 外国資本の参入による懸念 参入障壁の低さがもたらす影響 競争激化 オーバーツーリズムによる資源劣化 地元インストラクター・事業者の圧迫 改善に向けた提案 外資・外国人インストラクター向けの義務研修制度 サンゴ礁保護に関する条例の罰則強化 業務潜水の明確な定義と適用範囲の見直し キャパシティマネジメントと来訪者コントロール データの一元化と公開 潜水士免許は本来、「工事・救助等の業務潜水」における安全確保を目的とした資格で、レジャーダイビングのインストラクター業務とは内容が乖離している。2018年の規則改正により、外国人インストラクターは潜水士免許不要となる特例が認められ、日本人との間に不公平感が生じている。沖縄ではオーバーツーリズムの影響や外資参入の増加により、海洋事故とサンゴ礁破壊の懸念がますます高まっている。これらの課題を解決するためには、(1)外資・外国人向けのローカル知識研修義務化、(2)罰則強化によるサンゴ礁保護、(3)業務潜水の定義見直しによる公平性確保などの具体策が求められる。 【主な参考・出典】 厚生労働省「潜水士免許について」https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/index.html厚生労働省「高気圧作業安全衛生規則改正に関する告示(2018年)」 厚生労働省公表資料 (官報掲載分) 沖縄県「サンゴ礁保全行動計画」https://www.pref.okinawa.lg.jp/ (環境部 自然保護課資料など)環境省「サンゴ礁生態系保全推進調査報告」https ://www.env.go.jp/日本政府観光局(J
革新的な救助体験を実現!
SEAKERを活用したデモンストレーション 2025年1月16日、一般社団法人マリンレジャー振興協会(AMP)は、総務省の地域デジタル基盤活用推進事業の一環として、SEAKERを活用した海難救助のデモンストレーションを実施しました。この取り組みは、従来の捜索方法に革命を起こすもので、リアルタイム位置追跡技術を活用したピンポイント捜索と救助の実現を目指しています。本記事では、デモ当日の流れや参加者の声、ELTRES技術の可能性について詳しくお伝えします。 デモンストレーションの背景と目的 このデモンストレーションの主な目的は、漂流ダイバーの迅速な救助を可能にする技術の実証です。SEAKERが装着されたダイバーの位置情報を、ELTRES受信網を通じてリアルタイムで追跡し、従来の捜索と比較して大幅に効率的な救助方法を提示しました。 特に海域では、逆光や波の影響で視界が悪化し、捜索が困難になることがあります。しかし、ELTRES技術により、こうした課題を克服し、捜索範囲を極限まで絞り込むことが可能です。 デモンストレーション当日の様子 当初、デモは午前中に行われる予定で、行政や報道関係者も参加する計画でした。しかし、当日は海況が悪く、午後に実施時間を変更。最終的にmic21のアンバサダーのみが参加する形で行われました。午後でも海のうねりは残り、船は揺れる厳しい環境下での実施となりました。 デモの主な内容は以下の通りです : 漂流ダイバーの役を務めた参加者からは、「船が見えなくなった時の心細かった」という声がありました。ELTRES技術が正確に位置を捉え、船が自分たちのところへ真っ直ぐ救助に向かってきたことを確認しSEAKERの実力を実感できたとのことです。 サイレントドリフトダイビングの体験 デモの後半では、mic21アンバサダーたちに「サイレントドリフトダイビング」を体験してもらいました。この新しいダイビングスタイルは、浮上したダイバーの位置に船が迎えに行くため、船のエンジン音がなく、静かにダイビングを楽しめるのが特徴です。 さらに、この日は沖縄のホエールシーズン中で、鯨の歌声が海中に響く中でのダイビングとなり、参加者からは「これまでにない特別な体験だった」との声が上がりました。 SEAKERとELTRES技術の可能性 今回のデモンストレーションを通じて、SEAKERと
マリンレジャー事業者の安全対策
恩納村での講習会から学ぶ重要性 2025年1月15日、恩納村マリンレジャー協会主催の「水辺活動蘇生法講習会」に、mic21のアンバサダー4名が参加しました。この講習会は、マリンレジャー事業者向けの安全トレーニングとして開催され、CPR(心肺蘇生法)を中心に、溺水事故への迅速な対応や酸素供給の実践的な技術を学ぶ内容でした。本記事では、講習会で得られた知識や、参加者の視点から見た安全対策の重要性についてお伝えします。 講習会の概要と目的 恩納村マリンレジャー協会の講習会は、以下の目的を達成するために行われました: 講習会では、CPRの実践、溺水者の救助方法、医療用酸素供給の手順など、具体的かつ実践的な内容がカバーされました。 参加者の学びと気づき mic21アンバサダーの参加者たちは、トレーニングを通じて多くの知識とスキルを得ました。特に印象的だったのは、溺水時の迅速な人工呼吸が生存率を大きく左右するという点です。溺水後、人工呼吸を5分以内に実施すれば生存率が約90%にもなる一方、10分以上では大幅に低下します。このような緊急時の対応の重要性を学び、現場での即応力を高める貴重な機会となりました。 また、消費者目線での参加者の声も印象的です。「安全対策は全ての事業者が行っていると思っていたが、そうではないことに驚いた」とのコメントがありました。この気づきは、事業者選びの際に安全対策に注力しているかどうかを確認する重要性を再認識させるものでした。 安全対策にかかるコストの価値 マリンレジャー事業において、安全対策には一定のコストがかかります。例えば、酸素供給器材やAED(自動体外式除細動器)の導入、定期的なトレーニングの実施、ファーストエイドキットの準備などが挙げられます。それらは費用面で負担がかかる一方で、利用者の命を守るための不可欠な投資です。 特に沖縄県では、マリンレジャー事業者の安全対策が努力義務となっているため、取り組みに差が見られるのが現状です。事業者を選ぶ際には、以下のポイントをチェックすることが推奨されます: 安全対策に投資する事業者を選ぼう 恩納村の講習会を通じて、安全対策に注力する事業者の重要性が再確認されました。命に関わる緊急事態に備えるためには、コストを惜しまずに対策を講じることが必要です。そして、消費者としても、安全を重視した事業者を選ぶことで
総務省ICT/IoT利活用セミナーレポート
AMPの成功事例とデジタル化が生む地域社会の未来 1月14日、那覇市の沖縄県青年会館にて開催された「ICT/IoT利活用セミナー2025」に参加しました。このセミナーは、総務省沖縄総合通信事務所、一般社団法人沖縄総合無線センター、沖縄情報通信懇談会の共催で行われ、地域における情報通信技術(ICT)の活用がどのように課題解決をもたらすのかをテーマに開催されました。 内容は、総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)玉田康人さんによる基調講演と、一般社団法人マリンレジャー振興協会(AMP)の代表理事である安里繁信氏による講演でした。 基調講演「デジタルによる地域課題解決の最前線」 総務省大臣官房総括審議官玉田さんは「我が国が抱える課題とデジタルによる解決」をテーマに講演を行い、以下の重要なポイントを強調しました。 AMPによる「GPSトラッカーでの海域見守りサービス」の成功事例 続いて行われたAMP代表理事、安里繁信氏による講演では、「GPSトラッカーでの海域見守りサービス」の成功事例が紹介されました。この事業は総務省の情報通信技術利活用事業費補助金を活用して実現したものであり、沖縄全域にLPWA(Low Power Wide Area)通信網を構築した先進的な取り組みです。 安里代表理事は、次のような取り組みの成果について具体的に説明しました。 具体的な導入事例として、SUPやダイビングでの活用が紹介され、初心者の安全管理の重要性が強調されました。参加者からはこの技術を全国展開すべきだという意見も多く聞かれ、SEAKERの可能性が広セミナー参加者からの反応 講演後の意見交換では、参加者から以下のような反応がありました。 セミナー参加者の反応と意見 講演後の意見交換では、セミナー参加者から多くの質問や意見が寄せられました。 「LPWA技術が地方でどのように展開されるのか?」 安里氏は、沖縄での成功事例を全国の沿岸地域に展開する計画を語り、特に観光業や漁業が盛んな地域での活用に期待が集まりました。 「事前対応の具体例は?」 潮流の異常や急な天候の変化を察知し、活動者に警告を送るシステムが紹介されました。このような事前警告によって、事故発生の可能性を大幅に下げられるとのことです。 今後の課題としては、次の取り組みが求められます。 総務省大臣官房総括審議官玉田さんは講演の中で
安心の海、未来の安全
沖縄から広がる見守りサービスの革新 海洋活動は、観光産業や漁業、レジャーにおいて重要な役割を果たしています。しかし、その魅力とは裏腹に、海上での事故や遭難といったリスクが常に存在します。特に沖縄のように観光客が多く訪れる地域では、安全対策が非常に重要です。 過去の海難事故の事例を振り返ると、多くの場合、迅速な対応が遅れたことによって大きな被害が発生しています。たとえば、2019年に発生した大分県の観光船沈没事故では、乗客全員が救助されましたが、迅速な通報と救助活動がなければ悲惨な結果になっていた可能性があります。このような事例からもわかるように、海上でのリアルタイムな見守りサービスの重要性が増しています。 海の見守りサービスとは サービスの概要と目的 海の見守りサービスとは、海上での活動を監視し、安全性を確保するための技術やサービスの総称です。このサービスの主な目的は、海上での事故や遭難を防ぎ、万が一の事態が発生した場合に迅速に対応することです。特に、観光業が発展している地域では、観光客や地元住民の安全を守るために見守りサービスの導入が急務となっています。 技術の紹介 この見守りサービスには、最新の通信技術が活用されています。その中でも特に注目されているのが、LPWA(Low Power Wide Area)通信技術の一つであるELTRESです。この技術は、低消費電力で広範囲にわたる通信を可能にし、特に海上のような見通しが良い場所では100キロ以上の距離でも安定したデータ通信が可能です。また、ELTRESは低出力であるため、特別な免許が不要で、レンタル器材として貸し出すことも可能です。これにより、沖縄などの観光地では、観光客が手軽に安全装置を利用できる環境が整い、見守りサービスの実現が可能となりました。 海の見守りサービスのメリット 安全性の向上 海の見守りサービスを導入することで、リアルタイムでのモニタリングが可能となり、事故や遭難が発生した場合にはすぐに対応できるようになります。例えば、観光船が海上で異常を感知した際に、すぐに救助隊へ通知が行き、迅速な対応が可能となります。ELTRESのような技術を活用することで、通信範囲が広がり、離れた場所にいても安全が確保されます。これにより、被害を最小限に抑えることができます。 観光産業への影響 観光客にとって安全は最も